ハイブランドの代表格であるシャネル。
そのシャネルの創設者、ココ・シャネルの半生を描いた映画です。
ブランドに無知な私としては、シャネルって、こんな人だったの!? という驚きのある映画でした。
というわけで、『ココ・アヴァン・シャネル』の感想を語ってみたいと思います。
「私も見た!」という方も、「見ていない!」という方も、よかったらお付き合いください。
ただし、ネタバレ・あらすじを含みます。
お嫌な方は、ここまででお願い致しますm(._.)m
『ココ・アヴァン・シャネル』ネタバレ感想
記憶がおぼろになっている方&見ていない方のために、簡単なあらすじを。
流行は“だまし舟” ココは貧相? それともシック?
ココ・シャネルの、デザイナーとしての活躍を期待して見ると、ちょっと肩すかしに感じる映画かもしれません。
“アヴァン”とは、フランス語で“前”という意味で、題名を訳すと、『シャネルになる前のココ』という意味です。
つまり、ココがデザイナーへとなっていく過程に軸の置かれた映画なのですね。
一つ告白いたしますが、私、ブランドにはまったく無知で、シャネルとは、どちらかと言うと、女性らしいブランドだと思っておりました。
映画を見ていて、そういえば、元々は働く女性のためのブランドだったと聞いた覚えがあるな~、と思い出しました。
しかし、ココこと、ガブリエル・シャネルは、最初からデザイナーになりたかったわけじゃないというのは知らなくて、驚きました。
映画を見る限り、服を作ることには、あまり興味が向けられていなかったようです。
歌手とか、女優とか、そういうことがやりたかったみたいですよ?
でも、歌や芝居が好きで極めたいというより、男に頼らないでも生きていける人生とか、富とか名誉がほしかったようです。
孤児だった女の子がそれらを得る手段としては、芸能方面しか思いつかなかったのかもしれません。
でも、残念ながら、ココには芸能面での才能はなかった。
反面、お針子仕事は得意でした。好きではなかったかもしれませんが、向き不向きでいうなら、確実に向いていた。
そして、ココには、独自のファッションセンスというか、確固たる指向性があったのです。
ココは1883年生まれです。
西暦を見てもピンとこなかったので、日本人で同じ年に生まれた人を調べてみました。
『智恵子抄』の作者、高村光太郎が同じ年生まれです。また、鹿鳴館の開館式がこの年です。
うん。女性の社会的地位なんてない時代ですね。
フランスはどうだったのでしょう?
日本より多少は進んでいたかもしれませんが、ココの愛人・バルザンの邸宅にやってくる女性たちを見ていると、アントワネットの時代と対して変わらないような、女性であることを強調するドレスを良しとしていて、そのことに疑問も抱いていません。
現代から見ると、「古いな~」って感じますけど、私も、その時代のその場所にいたら、同じようなドレスを着て、ウエストを絞り上げて、ゴテゴテに飾り立てていたと思います。
だって、そういう時代ですから。
でも、ココには、それらのファッションが気持ち悪かった。
なんで体を締めつけるわけ? 動けないし考えられない。少しは頭使いなさいよ、となるわけです。
バルザンの邸宅に居候しながら、ココはボーイという男性と恋に落ち、小旅行に出かけます。
出かけた先で、ドレス姿の女性たちを品定めするのですが、めっちゃ辛辣です。
「まるで銀食器」「締めすぎて体が折れそう」「頭にメレンゲを乗せてる」「哀れな女たち」
いえいえ、ドレスに罪はないですし、そこまで貶さなくても(汗)
この時代、ウエストをコルセットでしぼり、ドレスから帽子から、レースや花や羽で飾るほうが普通なのです。
バルザンやボーイの服を借用したり、お手製の、今着ても通用しそうなワンピースやドレスを着るココのほうが異端なのです。
もちろん、現代に生きる私の目から見ると、ココのファッションのほうが馴染みがあります。
でも、不思議なのですよ。
映画を見ている間に、ふと、視点が切り変わって、今風に見えていたココが、貧相で、ひどく不格好にも見えてくるのです。
映画を見ている私の視線が、バルザンや、ココの友人となった女優のエミリエンヌの視線になる瞬間があるのです。
それはやはり、映画に映し出される時代から、ココが浮いていると脳が認識してしまうからなのでしょうね。
普段私は、自分が好きで服を選んでいると思っていましたが、結局、時代に操られているだけなのかもしれないな~と、この映画を鑑賞しながら思ったのでした。
“シャネル”以前もココはココ

イメージ画像
でも、ココは私みたいに、だまし舟にだまされたりしません。
これがココのすごいところだなと思います。
21世紀から見ている私でさえ、女性らしい華美なドレス姿の中で、今風のワンピース・ドレスのココが浮いて見えたり、バルザンの服を着て現れたときは、バルザンほどじゃないにしろ、変…と思ってしまったというのにです。
そういえば、バルザンに買ってもらったドレスを、「カーテンでしょ? 窓に吊っておいたわよ」なんて、ココは言います。
そう言われるとカーテンにしか思えなくて、笑ってしまいました。
バルザンは、そんなココを疲れる女と言ったり、他人の前で恥じたりします。
ココはココで、そんなバルザンを睨み付けます。
ココには、自分の出自に対するコンプレックスも強くありましたが、まだ何者でもない自分に対する怒りもありました。
バルザンへの怒りの中には、そんな、自分自身に対する怒りも含まれているような気がします。
こう書いてみますと、バルザンはちょっと、かわいそうでしたね。
彼は時代的には、普通の考え方の持ち主だと思います。上流階級の人だから、下々の気持ちが分からないのは仕方ないことです。
誰だって、自分の立場からしか考えることはできません。他人の立場になって考えるとか、なかなかできることではありませんよ。
それでもバルザンは、ココに結婚を申し込んでいます。下層の出であるココと結婚することは大反対されるでしょうから、一族と戦うとまで言ってくれました。
彼の立場を考えると、これだけでもすごいことじゃないでしょうか。
でも、ココは出て行きます。
そして、ココは成功します。
すごい。成功したこともすごいけど、上流階級の生活を蹴ってまで出て行ったことがすごい。
流されていれば楽だったでしょうし、安楽な人生を送れたでしょう。
でも、ココは、それを良しとしなかった。
結局、ココは、シャネル以前も以後も、ココなんです。
まっすぐに、心の向いている方に、ただひたすらに進んでいく。
バルザンを捨てて、ボーイの援助を受け、パリで店を出すというとき、ココはバルザンに「怖い」と心情をもらします。
それでも、安楽な場所には止まらなかった。
彼女の成功は素晴らしいけど、恐怖や不安に負けず、自分の信じるままに歩むココの頑固さが、なにより素晴らしいな~と感じたのでした。
映画情報
製作国/フランス
監 督/アンヌ・フォンテーヌ
出 演/オドレイ・トトゥ/ブノワ・ポールヴールド
日本での初公開年も2009年です。
この映画には原作があります。
エドモンド・シャルル=ルー氏の、同名小説が原作です。
こういう伝記物は、たとえば小説なら、誰が書くかによってお話のトーンは変わってきますね。
ココの恋愛遍歴に重きを置く人と、ココの野心に焦点を当てたい人では、違って当然です。
また、取材した相手によっても、違ったココが見えてきたりします。
結局、人間の心が“だまし舟”なんだな~、と思うのです。

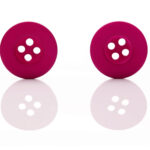

コメント